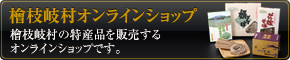農業
現状と課題
本村には農業で生計を立てている専業農家はおらず、自家消費用の農作物の栽培においても、農作業を行う人たちの高齢化や、近年増加している野生鳥獣による農作物の被害によって、遊休農地も目立つようになってきました。また、農業生産組合によるそばの生産が行われておりますが、今後新たな農業経営が開始されることは困難と予想されます。
遊休農地を増やさないためにも、小型農業機械の導入等によって農業生産の効率化を推進するとともに、こっちでーこ等の村でしか栽培できない付加価値の高い農作物生産の普及や、それを加工して商品化して観光と結びつけ、地産地消、6次産業化を図ることが求められます。 また、近年食品の安全・安心が非常に注目されておりますが、原発事故により県内産農作物をはじめとした食品については、放射性物質検査を行わなければならず、自家栽培の農作物においてもお客様へ提供する前には必ず検査を受けなければなりません。このことが、旬な農作物のタイムリーな提供に影響を及しています。迅速な検査やさらなる安全・安心性の向上と、生ごみや脱水汚泥を原料とした堆肥による有機栽培化を推進する必要があります。 地元で採れた物を地元で消費する地産地消と6次産業化の確立のためにも、安全・安心を確保するとともに、鳥獣被害を防ぎ、農業の振興を図らなければなりません。
主要施策
(1)地産地消の推進と観光との連携
- 村産のそば粉を使用し、裁ちそばをはじめとするそば料理を檜枝岐ブランドとしての価値を高めるため、そば栽培の拡大と有機栽培化による品質の向上を目指します。
- 独自の進化を遂げてきたこっちでーこ等の栽培の普及を図るとともに、昔から栽培が続けられているじゃがいも等の野菜の栽培を促進し、地産地消を推進します。
- お客様に提供する料理の原材料にするため、山菜やきのこの栽培を推進します。
- 食品の安全・安心を確保するために放射性物質検査の迅速な実施を行うとともに、村内産食品の安全安心を広く打ち出すことで新たな顧客確保を図ります。
- 村産堆肥を使用した有機栽培を支援し、農地の土質改良を図ります。
(2)遊休農地の利活用
- 遊休農地の現状と農地所有者の今後の意向についての調査を行い、遊休農地の解消と農地の集約による農業の効率化を図ります。
- 地産地消をさらに進めるため、遊休農地の有効活用を推進します。
(3)野生鳥獣による被害対策
- 鳥獣被害対策実施隊を中心としたパトロールや捕獲活動、捕獲方法の見直し等猟友会と鳥獣被害対策実施隊との連携により、農作物被害の軽減を図ります。
- 後継者の育成と狩猟免許取得者の増加を図るため、ニーズに合った補助金制度を創設するなどの支援をします。
その他
農地の売買・転用等について
農地を売買・転用する場合は農地法に基づき農業委員会、県の許可が必要となります。
許可を受ける場合は、下記のとおり申請書と添付書類を毎月10日までに農業委員会へ提出してください。
農地を耕作の目的のため、売買・貸借・贈与する場合
農地法第3条許可申請書 1部(農業委員会許可)
申請書の添付書類:申請地の登記簿謄本
耕作している農地を転用(家を建てる等耕作以外に利用)する場合
農地法第4条許可申請書 正副2部(県知事許可)
申請書の添付資料:
- 申請地の登記簿謄本(1通はコピーでも可)
- 公図(字限図)
- 転用地見取図(案内図)
- 位置図
- 土地の利用計画図(建物配置図)
- 建物平面図
- 資金証明書、残高証明書(不要の場合も有り)
※その他、必要に応じ書類の提出を求める場合があります。
他人に農地を借りたり、買ったりして転用する場合
農地法第5条許可申請書 正副2部(県知事許可)
申請書の添付資料:上記4条許可申請と同じ
※申請書の記載などご不明な点は産業建設課までお問い合わせください。
申請書:
農地法第3条許可申請書(PDF)
農地法第4条許可申請書(PDF)
農地法第5条許可申請書(PDF)
農業委員の募集について
現在の農業委員が令和5年7月19日に任期満了を迎えることから、新しい農業委員を下記により募集します。
1. 募集人数
・農業委員5名
2. 募集期間
・令和5年4月13日(木)~令和5年5月12日(金)まで
3. 募集内容
4. 推薦及び応募様式
・個人からの推薦(2名以上の連名が必要) 様式第1号
・農業関係団体等からの推薦 様式第2号
・応募 様式第3号
農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので公表します。
檜枝岐村農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
リンク
お問い合わせ先
- 産業建設課TEL:0241-75-2501